歯槽膿漏とは?具体的な症状は?原因と治療方法・治し方
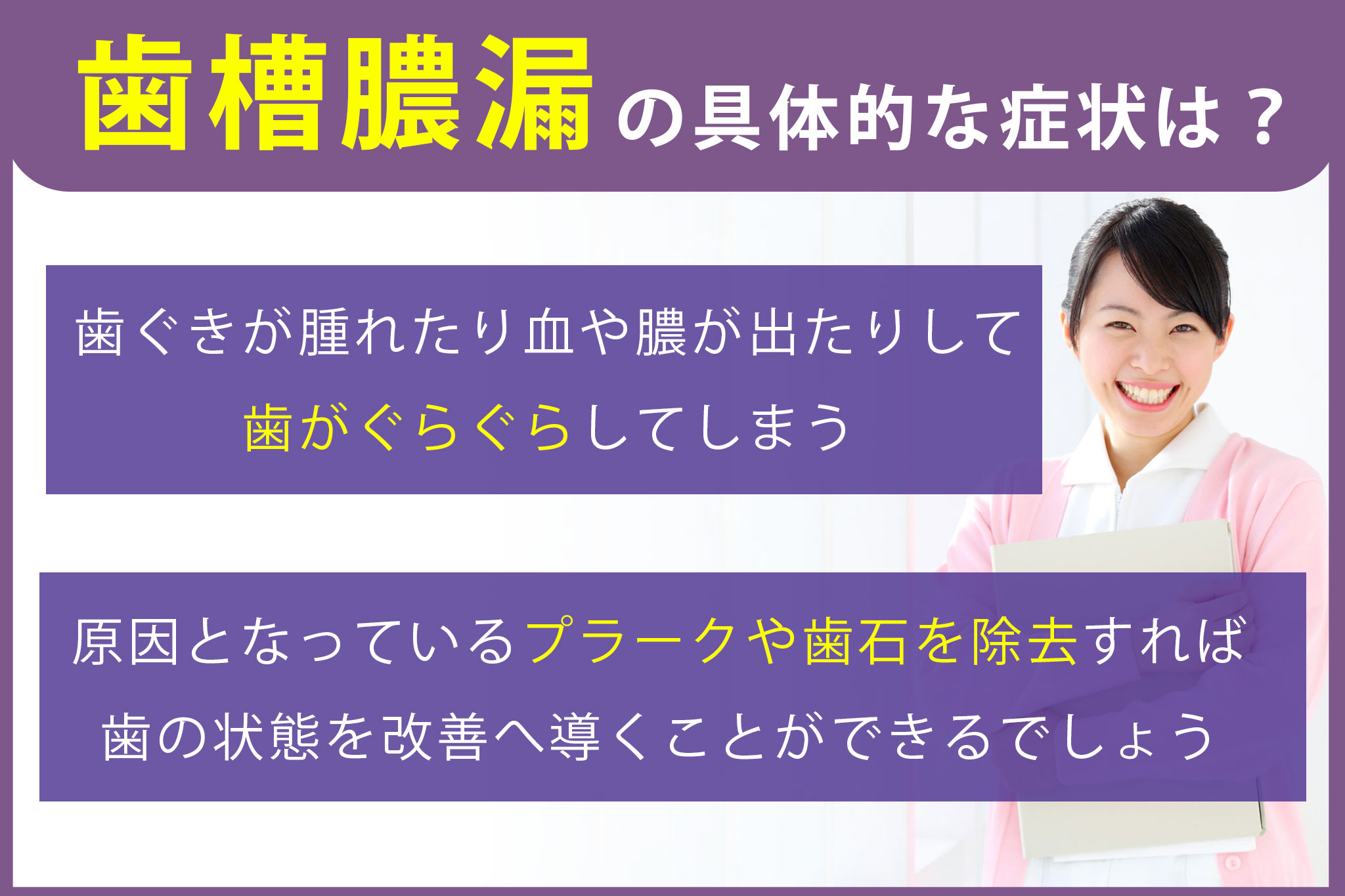
歯の健康状態を脅かす症状はさまざまありますが、今回ピックアップするのは「歯槽膿漏」です。
名前を聞いたことがあっても、具体的な症状にはイメージがつかないという人もいるかもしれません。
ぜひこの機会に、改めてどのような症状なのか確認し、原因と対策の知識を身につけておきましょう。
歯槽膿漏とは?
歯槽膿漏とは、歯を支えている歯ぐきに炎症が起き、腫れたり、血や膿が出たり、さらには歯そのものを支えきれなくなってぐらぐらしてしまう病気のことです。
歯槽膿漏は、現代人の生活習慣病のひとつともいわれている歯周病がもっとも深刻な状態まで進行した際に発生します。
そもそも歯周病とは、歯や歯ぐきにとって悪影響な細菌が増えていくことによって、炎症してしまうことで発生するものです。
歯周病の原因には歯垢(プラーク)などが挙げられ、毎日の生活の中で徐々に進行してしまう可能性があります。
初期や中期であれば毎日の心がけで進行を遅らせて改善へ導くこともできるかもしれませんが、ひとたび歯槽膿漏になってしまうと治療は大がかりなものになるので、注意が必要です。
歯周病はどのように進行するもの?
さらに詳しく、歯周病について解説していきましょう。
歯周病はまず、歯肉炎と呼ばれる症状が発生し、そのあとさらに進行していくと歯周炎という状態になっていきます。
歯肉炎は、歯ぐきが炎症して腫れてしまう症状のことです。
この炎症が続き、ますますひどくなっていくと歯と歯ぐきのあいだに隙間ができてしまいます。
本来、歯ぐきは歯をしっかり包み込んで固定しているものですが、隙間が深くなってしまうとやがて「歯周ポケット」という溝の発生につながります。
炎症の進行具合を見るときにもこの歯周ポケットを確認し、3mm以下であれば「歯肉炎」、4mm~6mmになると「歯周炎」と判断されます。
歯周ポケットに細菌が入り込み増殖していくと、そのうちに炎症はますます進んでしまいます。
そのうちに骨や歯根膜といった、健康な歯を支えるのに必要な組織が破壊されてしまい、歯周炎へと進行していきます。
そのあとさらに悪化して歯槽膿漏になってしまうと、骨までもが溶け出してしまい、歯を支えることが難しくなります。
この状態になってしまうと歯は非常に不安定になり、ちょっとしたものを噛んだり、少し力を入れただけでぽろりと抜けてしまうこともあります。
歯周病は「完全に治す」のではなく、「よりよい状態へ導く」ことが重要ですから、なるべく早めの対応が欠かせません。
歯槽膿漏の治療方法
軽度の歯周病なら、歯のケア方法を見直すことによって改善へ導ける可能性が高くなります。
原因となっている歯垢(プラーク)や歯石を除去すれば、歯の状態を改善へ導くことができるでしょう。
進行していくと歯周ポケットにもアプローチしなければいけなくなり、入り込んでしまった歯石をかきだして除去しなければいけません。
さらに進行している場合には、外科処置も必要になります。
まずは現在の進行具合を確かめるための検査を行い、歯ぐきや口内の環境を確認します。
細菌の状態によっては、薬によって細菌の繁殖や活動を抑えたり、溶けだしてしまった骨を人工骨で補填したりといった治療を行います。
さらに口腔内写真やレントゲン写真を撮影し、表面では見えにくい部分に至るまで、どのような状態になっているか確認します。
嚙み合わせを確認するために、歯型を作成するケースもあります。
歯石の除去などの治療だけで改善が見られないときには、フラップ手術と呼ばれる手術や歯周組織再生治療も行います。
進行するごとに大がかりな治療になりますから、なるべく早めの治療が大切です。
そして同様に、現段階では好ましい環境である人も深刻化しないよう日頃から予防する行動も必要不可欠です。
歯槽膿漏を予防するためには
近年、予防歯科という言葉が知れ渡ってましたが、健康な歯をキープするためには日頃から歯周病や歯槽膿漏を予防する姿勢が重要です。
生活の中で、次のようなポイントを気にかけましょう。
◇定期的に歯科クリニックに通い歯垢や歯石を除去する
◇食後にしっかり歯磨きをする習慣をつける
◇正しい歯磨きの方法を覚える
◇フロスや歯間ブラシも使う
◇ストレスをためないように心がける
◇タバコは控える
◇食生活を見直し栄養バランスのとれた食事を意識する
これらを「思い出したときにときどき実践する」のではなく「毎日無理のない範囲で意識する」ことが、なによりの予防につながるでしょう。
まとめ
歯周病は現代人の生活習慣病のひとつと言われていますが、放置していて深刻化してしまうと歯が自立できないほどの状態になってしまいます。
知らず知らずのうちに細菌が繁殖することによって、歯ぐきが衰えたり、歯を支えている骨が溶けたりといったトラブルにもつながりかねません。
できるだけ早めに医師へ相談し、適切な治療を行うとともに高い意識で予防しましょう。
本院 院長

林 清誠
保有資格
- インプラントアソシエイトフェロー(の称号)認定
- 口腔インプラントフェロー(の称号)認定
- JIAD口腔インプラント認定医
- JSOI口腔インプラント専修医
- 軽度認知障害支援歯科医
- 口腔インプラント専門医
詳細を見る
| 経歴 | |
|---|---|
| 1990年 | 八尾市立永畑小学校 卒業 |
| 1993年 | 私立清風中学校 卒業 |
| 1996年 | 私立清風高等学校 卒業 |
| 2003年 | 愛知学院大学 歯学部 卒業 |
| 2003年 | 大阪大学歯学部付属病院 口腔治療科 入局 |
| 2004年 | 医療法人中村歯科 勤務 |
| 2005年 | 小田歯科 勤務 医療法人布川矯正歯科 非常勤務 |
| 2006年 | あべの歯科 医院長就任 |
| 2007年 | 清誠歯科 開業 |
| 2010年 | 社団法人 日本歯科先端技術研究所大阪 理事 就任 |
| 2011年 | 愛知学院大学歯学部大阪府同窓会 大阪愛歯会 理事 就任 |
| 2011年 | 医療法人清誠 清誠歯科 開設 |
| Certificate | |
|---|---|
| 2003年 | Akashi Orthodontic Research Group LEVEL ANCHORAGE SYSTEM |
| 2005年 | Straumann Dental Implant System ‘Basic Course’ |
| 2006年 | FEBS CLINICAL DENTISTRY TRAINING COURSE |
| 2006年 | C.E.R.I研修会 大阪コース (Clinical Endodontic Reseach Institute) |
| 2008年 | Daemon System Certification |
| 2009年 | A Comprehensive Spline Implant Training Course (Advance) |
清誠歯科は患者様の歯の健康を追求することを第一に、最高の治療環境を提供することにこだわっています。
例えば、治療にあたって医師それぞれの専門知識を活かした治療方針カンファレンスを行い治療の質を高めています。
そして、各種セミナーや学会の参加によって常に最新の技術習得に努める努力を続けています。
また、歯科衛生士・助手においても、定期的に勉強会を開催するなど、医療サービスの向上に努めております。
また、駐車場を設けて、お車でご来院される患者様へも配慮させていただいたり、診療時間を日曜日や平日の20時半まで伸ばしたりというように、通院しやすい環境を整えることで、最後まで治療していただけるようにしています。
所属団体
- 日本歯科医師会
- 大阪府歯科医師会
- 大阪大学歯学会
- 日本矯正歯科学会
- 日本歯科保存学会
- 日本歯周病学会
- 公益社団法人 日本口腔インプラント学会
